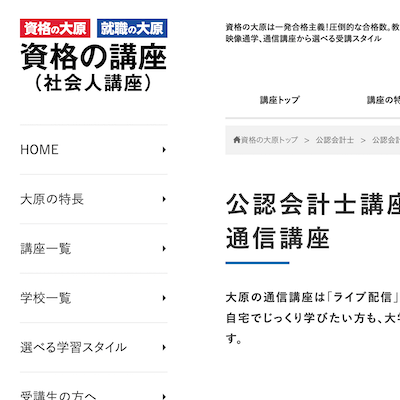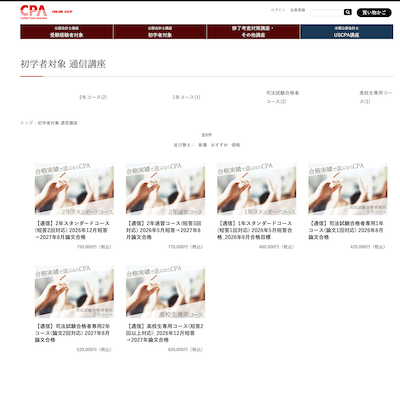社会人として働きながら公認会計士を目指すのは、決してかんたんではありません。しかし、計画的な学習の継続と正しい戦略により、合格は十分に実現可能です。この記事では、仕事と学習の両立を目指す社会人の方に向けて、学習時間確保の仕方、予備校のメリット、モチベーション維持のコツなどを詳しく解説するので参考にしてください。
働きながら公認会計士を目指す際に知っておくべきこと
社会人になってから公認会計士を目指すのは非現実的ではないか、という不安を抱えている方は少なくありません。実際、試験前でも仕事を休めないため、勉強時間が確保しにくく、仕事の疲れも重なり学習効率は下がりがちです。ただでさえ、公認会計士の試験は非常に難易度が高いので、働きながら公認会計士を目指すのは困難です。ここでは、働きながら公認会計士を目指す際に知っておくべきことを紹介します。
合格率
社会人受験生の合格率について触れておきましょう。2021年度の公認会計士試験の全体平均合格率は9.6%で、会社員や公務員といった社会人層の合格率は、おおよそ4〜5%とされています。確かに大学生に比べると低い数値ではありますが、この数字は、限られた時間を有効活用し、継続的な努力を重ねれば、社会人であっても十分に突破可能な試験であることを示しています。
しかし、いうまでもなく、公認会計士合格までの道のりはかんたんではありません。どんなに順調に進めたとしても数年単位の時間がかかるため、綿密な学習計画と長期的な視野が必要です。
情報収集
受験勉強のスタート期から、さまざまな情報を収集しておくことが大事です。たとえば、監査法人の採用動向を理解しておきましょう。コロナ禍の影響で一時的に採用枠が絞られた時期もありましたが、近年は景気の回復とともに採用意欲が再び高まりつつあります。さらに、会計業界では「資格を持っているかどうか」が重視される傾向が強く、社会人出身であっても学歴や前職に関係なく、公認会計士資格を取得していれば十分に転職のチャンスがあります。むしろ、今の監査法人の採用市場は「売り手市場」とも言われており、合格後の就職先に過度な心配は不要です。
年齢に応じたアピール方法
年齢に応じたアピール方法も、合否や転職活動の成否に大きく影響します。たとえば、20代であれば「若さ」という武器を最大限に活用することで、ポテンシャル重視の採用枠に入りやすくなるでしょう。加えて、社会人としての経験や業界に対する熱意、将来への成長意欲を具体的に伝えることが大事です。一方で、30代以上の受験生には別の強みがあります。これまでの職務経験から得たビジネススキルやほかの資格との相乗効果は、即戦力としての魅力につながります。
採用側も、即戦力として期待できる人材には高評価を与える傾向があり、アピール次第で年齢のハンデは十分に克服可能です。若さという武器をもつ20代とは異なり、30代はアピールポイントを考えた転職活動が求められます。
トレーニー制度の活用が大事
試験に合格する前でも転職できる監査法人や会計事務所が存在することを、知っておきましょう。また、働きながら学ぶ社会人受験生に対して、柔軟な制度やサポートが整っている職場もあり、難易度が高い受験を控える受験生にとってまたとない環境です。「監査トレーニー制度」を設けている監査法人では、試験前の休暇取得や残業制限などの支援が受けられる場合もあります。こうした制度を活用すれば、収入を得ながら実務経験も積み、受験勉強にも集中して取り組めるという、非常に効率的な環境を手に入れられるのでおすすめです。
実際、試験合格前に監査法人へ転職し、アシスタントとして働きながら合格を目指すルートは、実務経験を効率的に積めることもあり、非常に魅力的な選択肢です。収入を確保しつつ実務理解が深まり、学習意欲の維持にもつながります。
社会人の合格は不可能ではない
働きながら公認会計士を目指すことは、決して無謀な挑戦ではありません。国家資格の中でもトップクラスの難易度を誇る試験である以上、かんたんな道のりではありませんが、適切な準備と強い実行力があれば、働きながらでも合格を勝ち取ることは可能です。
むしろ、豊かな社会経験と現実的な視点を武器に、新たなキャリアを切り拓く助けとなる場合もあります。
働きながら公認会計士試験を目指すメリット
社会人として安定した生活を送りながらも、やりがいのある仕事に就きたい、キャリアアップを目指したいと考えたとき、国家資格の取得を視野に入れる人は少なくありません。なかでも公認会計士は、医師・弁護士と並ぶ「三大国家資格」として、圧倒的な信頼と地位を誇る専門職です。働きながら目指すのはかんたんではありませんが、努力に見合うだけの価値と可能性がある職業です。ここでは、公認会計士試験合格を目指すメリットについて解説します。
高い社会的ステータス
公認会計士資格を取得する最大の魅力は、社会的なステータスの高さにあります。監査業務を独占的に実施できるのは公認会計士だけであり、業務対象には上場企業や大手法人など、日本経済を支える存在が数多く含まれます。業務には、高い倫理観と正確な判断力を求められ、つねに重い責任をともないますが、そのぶん社会的信用も極めて高いのが特徴です。専門知識を活かして企業経営の健全性を支える、非常に意義のある職業です。
高収入
収入面においても、公認会計士は極めて恵まれた環境にあります。厚生労働省の「平成30年賃金構造基本統計調査」によると、公認会計士および税理士の平均年収は約892万円でした。これはあくまで給与所得者としての平均であり、独立開業すればその上限はさらに広がります。専門性が高く信頼性のある資格だけに、長期的に高収入を維持しやすいという点も魅力です。
安定している
公認会計士の業務は、景気の波に左右されにくいという特徴もあります。企業が存在し、決算がある限り、監査という業務は絶えず必要とされます。経済が停滞しても、監査法人や会計事務所の仕事がゼロになることは考えにくく、将来にわたって一定の需要が見込まれる職種です。また、年齢を重ねたあとのキャリアの幅広さも、公認会計士ならではの利点です。たとえば、監査法人勤務には定年があるものの、コンサルタントや社外役員、企業アドバイザーとしてのニーズはなくなりません。
専門的な知識と経験を武器に、年齢を問わず長く活躍できる可能性があるのも魅力的です。退職後に中小企業の支援や地域経済への貢献といった新たな形で再スタートを切る会計士も多く見られます。
一定の経験と実績を積めば、年齢を重ねても安定した仕事が見込める点は、大きな安心材料でしょう。こうした安定性の高さは、長期的なキャリア形成を考えるうえで非常に大きなメリットです。
キャリアの選択肢が多い
働きながら公認会計士試験を目指すメリットとして、キャリアの選択肢が大きく広がる点が挙げられます。一般企業に勤めていると、どうしてもその会社内での昇進や異動にキャリアの方向性が限定されがちですが、公認会計士資格を取得すれば、監査法人、税理士法人、事業会社の経理・財務部門、あるいは独立開業と、多岐にわたるフィールドで自分の力を試せます。
ひとつの会社に縛られず、スキルを武器に自由な働き方ができるようになるという点は、資格を取得する大きなメリットです。
公認会計士試験合格に必要な勉強時間の目安
公認会計士試験は、非常に高い専門性が求められる試験のため、合格までには膨大な学習時間が必要とされます。一般的に、合格に必要な勉強時間は3,000時間以上とされており、社会人がこの目標を達成するには、相応の計画と覚悟が不可欠です。1日5〜6時間の学習を約1年半から2年続ける必要があります。しかし、フルタイムで働きながらこの時間を捻出するのは現実的に厳しく、多くの人が途中で学習を断念してしまう原因にもなっています。
なぜ3,000時間必要なのか
公認会計士試験では、短答式試験と論文式試験という二段構えの試験制度が特徴です。短答式に合格した人だけが、論文式の受験資格を得られるものの、その有効期限は2年間しかありません。すでに会計や法務の知識がある人であれば、学習時間を短縮することもできるでしょう。しかし、そうしたバックグラウンドがない社会人にとっては、基本から積み上げていかなければなりません。その分、学習期間はどうしても長期におよんでしまいます。限られた時間の中でふたつの試験形式に合格するためにも、全体の勉強時間をしっかり確保しておく必要があるのです。
短答・論文で分けて戦略的に学ぶ
社会人が限られた時間のなかで合格を目指すには、試験制度を踏まえた効率的な学習が求められます。たとえば、まずは短答式試験の合格を目指し、その後に論文式へとシフトする段階的なアプローチが有効です。短答対策では、財務会計論や管理会計論といった計算中心の科目を徹底的に反復することで、基礎力を養いましょう。合格後は、論文式試験に求められる理論の記述や応用的な問題演習に集中する形が理想的です。
とくに財務会計論は、理論と計算のバランスが肝心です。管理会計論は計算練習を通して全体像を理解し、監査論では制度の趣旨や考え方を押さえながら進めていくと効果的です。企業法は暗記量が多いため、早期に取り組み、繰り返し復習することが不可欠です。
勉強時間を確保する
社会人にとって一番の難関は、やはり勉強時間の確保です。仕事を終えた後は体力も気力も消耗しがちで、机に向かう気力を保つのはかんたんではありません。そこで重要になるのが、スキマ時間の活用です。たとえば、早朝に30分だけ早起きして出勤前に学習する、通勤中に音声講義や暗記カードを活用する、昼休みに要点だけを見直すなど、小さな積み重ねが、結果として大きな学習時間となります。仮に1日30分ずつ学習した場合でも、1年間で150時間以上の勉強時間が確保できるのです。
モチベーションを維持する
仕事と勉強の両立は、思った以上に精神的な負荷がかかります。とくに、思うように学習が進まない日が続くと、焦りや不安でモチベーションが落ちやすくなります。しかし、焦って一気に詰め込もうとしても、かえって効率は落ちてしまいがちです。大切なのは継続することと、学習スケジュールを大きく崩さないことです。予定より少し遅れた場合は、学習計画を見直し、軌道修正する柔軟さも必要でしょう。
勉強方法は主に2つ
公認会計士試験は、非常に難易度の高い国家試験として知られています。とくに社会人として働きながら挑戦するとなると、時間的な制約や体力的な負担もあり、合格はかんたんではありません。しかし、効率的な勉強法を選び、自分に合ったスタイルで学習を継続することで、合格を勝ち取ることは十分に可能です。社会人が公認会計士を目指す場合、代表的な勉強方法は「専門学校・予備校を利用する方法」と「独学で進める方法」の2つに大別されます。
それぞれに特徴や利点、注意点があるので、自身の性格やライフスタイル、経済状況などを踏まえて最適な方法を選びましょう。
専門学校・予備校に通う
まずひとつ目の方法は、専門学校や予備校を活用して学習を進める方法です。これは現在、多くの受験生にとってスタンダードな選択肢となっています。最大の魅力は、プロの講師が作成した体系的なカリキュラムに沿って、効率よく勉強を進められる点です。公認会計士に限らず、資格試験の試験傾向は変化することがあります。専門学校や予備校の講師は、実施された試験の傾向を分析し、対応できるよう、教材や指導内容を最新版にブラッシュアップしています。試験傾向を網羅した、最新の教材に触れられることは、合格にあたって非常に大きなメリットといえるでしょう。
また、わからない部分があれば、すぐに講師に質問できる環境も整っているため、独学では乗り越えにくい壁もスムーズに解決できます。また通学講座では、同じ目標をもつ仲間たちと出会える点も見逃せません。
孤独になりがちな勉強生活において、切磋琢磨できる存在がいることは、モチベーションの維持に大きく寄与します。勉強仲間と情報交換したり、互いを励まし合ったりすることで、継続力や粘り強さが形成されやすいでしょう。
通学がむずかしい場合には、短期集中講座や特定科目に特化した講座を利用するのもひとつの手段です。近年では、いそがしい社会人のニーズに合わせたオンラインによる講義も広く展開されています。
自分のスケジュールに無理なく組み込める方法を選ぶことが、学習の継続と成功につながるカギとなります。ただし、専門学校や予備校に通う場合、授業料は数十万円単位になることもめずらしくなく、高額な費用は無視できません。
また、仕事との両立がむずかしい時期には、通学時間を確保することがストレスとなる可能性もあるため、自分の生活ペースと相談しながら判断する必要があります。
独学で学ぶ
一方、独学で公認会計士試験を目指すという選択も、多くの社会人にとって現実的な方法です。経済的な負担を抑えられるという意味では非常に有利であり、教材費のみで学習を進められる点は大きな魅力です。非常にコストパフォーマンスにすぐれた学習方法といえるでしょう。また独学は、自分のペースで自由にカリキュラムを設計できます。苦手な分野に時間を多く割いたり、得意分野をすばやく終わらせて時間を節約したりと、柔軟な学習が可能です。
周囲の進度に左右されることもなく、マイペースで集中できるというのは、自己管理能力が高い人にとって大きな利点です。さらに現在では、独学者を支援するツールやコンテンツも非常に充実しています。
たとえば、Web講座やDVD教材、YouTubeの無料講義動画など、予備校に通わずともプロの解説に触れられる機会は豊富です。書店に並ぶ参考書や問題集も充実しており、独学者でも効率よく学べる環境が整っています。
ただし、独学には、自己管理ができなければ勉強の進行が遅れ、試験に間に合わないデメリットがあります。働きながら学習する場合、仕事の疲れや突発的な残業によって、予定どおりのスケジュールを維持するのはかんたんではありません。
また、学習の過程で疑問が生じた場合、解決までに時間がかかることも多く、効率面ではどうしても専門学校に劣るでしょう。さらに、精神的な孤独感に陥りやすいのも、独学の難点です。
周囲に勉強仲間がいないため、モチベーションを維持するのがむずかしく、独学で成功するためには、強い意志と継続力が欠かせません。