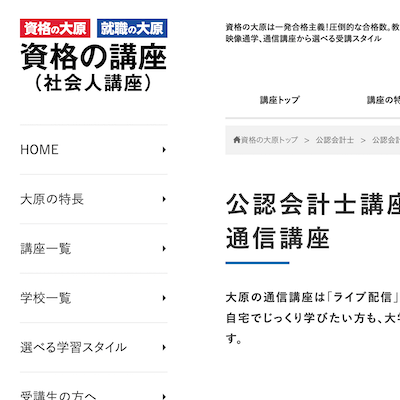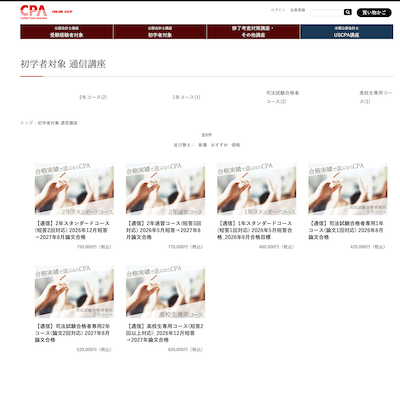公認会計士は合格率が低い難関資格として知られているため「社会人として働きながら合格を目指すのは難しいのでは」と考えている人も多いでしょう。今回は社会人で公認会計士を目指す人向けに、試験の難易度や学習のポイント、働きながら合格を目指すメリットやスキルを活かせる職種についても詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
公認会計士の難易度について
公認会計士は難易度の高い資格として知られており、十分な勉強時間の確保が不可欠です。ここでは、公認会計士の概要やレベルなどを詳しく解説します。公認会計士資格の概要
公認会計士は監査や会計に関する専門知識を有する人に与えられる国家資格です。業務の幅が非常に広く、マルチな能力が身につくのがメリットとなります。とくに監査業務は公認会計士のみが許されており、地位や信頼性が高い資格のひとつとして知られています。公認会計士は難関資格のひとつ
公認会計士は社会的な責任が大きいことから資格試験の難易度も高く、医師・弁護士に並ぶ三大国家資格であるのが特徴です。2024年の公認会計士試験は合格率7.4%であり、難易度の高さが分かります。試験内容は短答式試験が500点分と論文式試験が700点分あり、とくに短答式試験の難易度が高いです。短答式試験については科目ごとの合格制度がないため、財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目すべてに合格しなければなりません。つまり、4科目のうちひとつでも不合格となった場合には、再度4科目すべてを受験し直すことが必要です。
対して、論文式試験は会計学・監査論・企業法・租税法・選択科目の5科目で構成されていますが、科目別合格制度が認められていることから、一部合格した科目については受験し直す必要がありません。
公認会計士の受験資格
公認会計士には受験資格がありません。国家資格には受験のための条件が設定されているものが多いですが、公認会計士は年齢や経験、取得資格などに関係なくだれでも受験可能です。公認会計士試験合格に必要な勉強時間
公認会計士になるために必要な勉強時間は最低でも3,000時間であるといわれています。金融庁の資料では公認会計士資格の取得には約2年間・3,000〜5,000時間におよぶ勉強が必要であると記載されており、単純計算で1日6時間以上を2年間継続しなければなりません。公認会計士資格は勉強すべき範囲が非常に広く、合計9科目をしっかりと掘り下げて学習する必要があります。また、専門性が高いことや試験の問題数が多いことも難易度の高さの要因であり、2年間程度の学習スケジュールで試験対策を進めなければ合格は難しいでしょう。
働きながら公認会計士試験に合格するのは可能?
先述の通り、公認会計士は合格までの道のりが非常に長く、2年単位で学習のスケジュールを立てなければなりません。そのため、社会人として仕事をしながら合格を目指すことが難しいのは事実です。しかし、実際に働きながら公認会計士に合格した人も数多くいます。ここでは、社会人が公認会計士合格を目指す際のポイントや注意点などを詳しく解説します。
公認会計士は働きながら取得することも可能
公認会計士の資格は社会人が働きながら取得することも可能です。実際の公認会計士の合格者は半数以上が学生ですが、会社員が6.5%、会計事務所員が4.9%、そのほかの社会人が1.8%と、合わせて13%以上の合格者が働きながら資格を取得しています。また、合格者のうち18.6%は無職、7.9%は専修学校・各種学校受講生ですが、中にはアルバイトなどをしながら資格勉強をしていた人もいます。さらに、合格者の34.8%は25歳以上であることから考えると、合格者のうち2〜3割程度は仕事と資格勉強を両立していたと推測可能です。
もちろん、3,000〜5,000時間にもおよぶ勉強が必要である点を考えると、働きながら公認会計士合格を目指すのは決して簡単なことではありません。しかし、実際に社会人でも合格を掴み取っている人が多数いることから、コツコツと試験勉強を続けられる人であれば十分に合格の可能性もあるといえます。
働きながらの合格を目指すために押さえておくべきポイント
社会人として働きながら公認会計士の取得を目指すのであれば、限られた時間を有効活用できるような対策を取ることが重要です。まずは公認会計士試験の出題範囲や試験科目、試験内容、出題傾向などをしっかりと分析しましょう。そのうえで合格を目指す具体的な時期を決めたら、受験時期から逆算して試験現況の計画を立てます。勉強の際は単なる暗記ではなく理解することを大切にして、応用問題や論文問題にも対応できるよう心がけましょう。
また、働きながら公認会計士合格を目指すうえでもっとも重要なポイントは、とにかく勉強を継続することです。社会人として働いていると、思うように勉強時間を確保できなかったり、疲れで計画通りに学習を進められなかったりする日もあるでしょう。
しかし、うまくいかないときがあっても継続を第一に考えて勉強を続けることで、合格に向かって一歩一歩着実に進んでいけるでしょう。
社会人が独学で試験合格を目指す際の注意点
公認会計士を目指す人の多くは資格取得のために予備校に通っています。予備校では学習内容そのものの解説はもちろん合格まで効率よく勉強できるノウハウも提供してもらえるため、資格取得に向けた明確な学習計画・学習内容に沿って日々の勉強を進められるのが魅力です。しかし、中には仕事の都合や勤務形態の関係で予備校を利用するのが難しく、独学での公認会計士受験を目指したい人もいるでしょう。先述の通り、公認会計士を目指す場合は2年間を目安として学習スケジュールを立てるのが一般的です。
しかし、予備校なしで独学での合格を目指す場合には、さらに長期的なスケジュールで学習することを覚悟しておく必要があります。各予備校が出版している試験対策本や過去問などをうまく活用しながら、頻出範囲をメインとして効率よく試験対策を行いましょう。
働きながら公認会計士資格を取得するメリット
公認会計士資格は非常に難易度が高い試験であるため、勉強時間の確保が難しい社会人受験にはあまりメリットがないと感じる人もいるでしょう。しかし、働きながら試験勉強に取り組むことにはいくつかのメリットがあります。ここでは、社会人として仕事をしながら合格を目指すことのメリットを3つ紹介します。収入を得ながら資格取得を目指せる
公認会計士試験に働きながら挑戦することの大きなメリットは、収入を得ながら合格を目指せることです。たとえば試験勉強を効率よく進めるために予備校を利用する場合、数十万円単位の費用がかかります。まとまった授業料を支払ったうえ、合格までの約2年間を無収入で過ごすことを考えると、貯金が底をつきてしまったり、生活が苦しくなったりするという人も少なくないでしょう。
社会人として仕事をしていると試験勉強との両立が難しくなるなどのデメリットもありますが、たとえ合格時期が遅れたとしても、安定した収入を得ながら公認会計士を目指せることは大きなメリットです。
不合格の場合でも就職活動に困らない
公認会計士は医師や弁護士に並ぶ最難関試験であるため、不合格となった場合の選択肢についても考えておくのが賢明です。無職で不合格となった場合は就職先を探す必要があり、また、再度公認会計士を目指して受験する場合は無収入期間が延びるため、相応の貯蓄が必須条件となります。対して、社会人として働きながら公認会計士を目指すケースでは、途中で受験を諦めたり不合格になったりしてもそのまま現在の職場で働き続けることが可能です。
不合格を受けて改めて職場を探す必要がないため、メンタル面での不安も軽減されるでしょう。さらに、再受験を決めた場合でも収入を途切れさせずに次回の試験まで学習を継続できます。
社会人経験を合格後の仕事に役立てられる
働きながら公認会計士を目指すケースでは、職種によっては公認会計士資格取得後の就職活動や仕事に社会人経験を活かすことも可能です。とくに金融系や経理関係の仕事に携わっている人は、公認会計士取得後の就職先でも身につけてきた知識・スキルを存分に活用できるでしょう。また、就職活動の際に自分の強みとしてアピールすることも可能です。
監査トレーニーとして働きながら合格を目指す手も
先述の通り、公認会計士取得を目指す人の約2〜3割程度は社会人として働きながら資格勉強をしています。収入を得ながら公認会計士を目指したい人は、監査トレーニーとして働くことで公認会計士の実務に触れながら試験合格を目指すのもひとつの選択肢です。ここでは、監査トレーニーの概要や収入などを詳しく解説します。
監査トレーニーの概要
そもそも監査トレーニーとは、公認会計士の補助スタッフとして監査法人で働ける制度です。監査トレーニー制度を導入している監査法人は一部ですが、直接公認会計士の指導を受けてサポート業務に携われるため、実務的な知識・スキルをしっかりと身につけられます。現在は少しずつ監査トレーニー制度を採用する監査法人が増加しており、求人数も増えています。
監査トレーニーとして働くための条件は監査法人によってまちまちですが、公認会計士資格の取得を目指していることのほか、実務経験がある人・短答式試験に合格している人・特定の科目に合格している人などを入社条件としているのが一般的です。
監査トレーニーとして働きながら資格取得を目指すメリット・デメリット
監査トレーニーとして働きながら公認会計士資格の取得を目指すことの大きなメリットは、勤務時間に学べることをそのまま試験にも活かせる点です。基本的に社会人受験においては平日の勉強時間は数時間程度しか確保できませんが、監査トレーニーとして働いていれば、勤務時間も試験勉強の一部になります。また、中には監査トレーニーの予備校の費用を補助している監査法人もあります。さらに、公認会計士試験に合格したあとはそのまま同じ監査法人で働けるため、就職先選びの手間がないこともうれしいポイントです。
ただし、監査トレーニーは求人数が多くないことから競争率が非常に高く、希望する監査法人でスムーズに採用してもらえるかが分からない点がデメリットとして挙げられます。