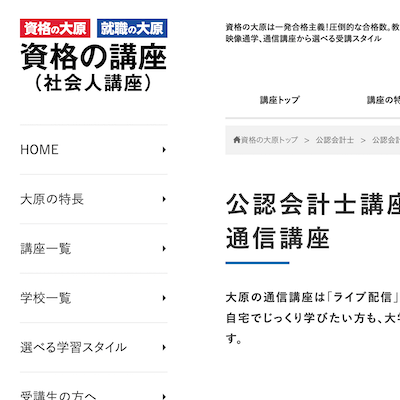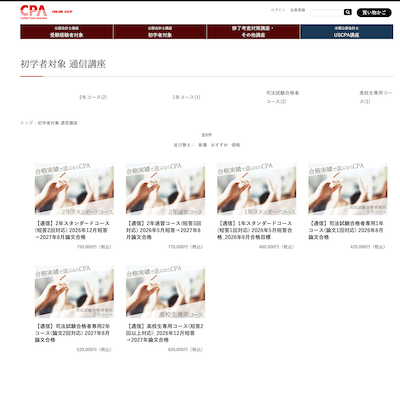医者や弁護士と並ぶ国家資格とも評される公認会計士。公認会計士しか行えない独占業務があり、安定性が高い職業とされる一方で、資格の取得難易度は極めて高いと言われています。本記事では、高卒で公認会計士は目指せるのかについて詳しく紹介していきます。公認会計士を目指すか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
高卒でも公認会計士を目指すことは可能
公認会計士は取得難易度が極めて高い資格ですが、最終学歴が高卒で大学卒業資格を持たない人でも、目指すことは十分可能です。ここでは、高卒でも公認会計士を目指せる理由を紹介します。受験資格
2025年時点で、公認会計士には資格取得試験の受験資格が一切設定されていません。年齢や国籍、最終学歴、性別などの条件が一切存在しないため、誰でも受験し、試験に合格すれば資格の取得が可能となっています。最終学歴が高卒の人でも、勉強して試験にさえ合格できれば公認会計士の資格を取得可能です。試験の一部免除が受けられる条件
公認会計士の試験では、会計専門職大学院の修了者や税理士試験・不動産鑑定士試験の合格者は一部科目の試験が免除される制度が用意されています。特定の資格を取得していれば、より公認会計士の資格を取得するハードルが下がりますが、この資格を取得していなければ試験を受けられないといった資格は存在しません。
公認会計士に向いている人の特徴
公認会計士に向いている人の特徴としては、努力できる人や正義感のある人、コミュニケーション能力がある人などが挙げられます。ここでは、公認会計士に向いている人の特徴をまとめて紹介するので、目指すか迷っている人はぜひ参考にしてください。努力できる人
公認会計士は、数ある資格の中でも取得が難しい難関資格であり、取得するためには約3,000~4,000時間ほど勉強する必要があると言われています。合格率は10%前後で、しっかりと勉強に取り組んでも取得は簡単ではありません。そのため、努力が苦手な人は資格を取得できる前に挫折する可能性が高いと考えられます。公認会計士を目指す際は、最後まで努力を続けられるかよく考えてみると良いでしょう。
正義感のある人
公認会計士とは、会社の経理が正しく行われているかを確認する仕事です。どのような時でも絶対に公正な立場で判断を下す必要があり、不正やミスを見逃すことは許されません。そのため、正義感が強い人に向いています。コミュニケーション能力がある人
公認会計士は、人と関わるシーンが多い職業です。そのため、業務を円滑に進めるためには高いコミュニケーション能力が求められます。コミュニケーションをとることに苦手意識がある人やプレゼンが苦手な人、できれば人と接する機会が少ない職に就きたいと考えている人は注意が必要です。高卒から公認会計士を目指すメリット・デメリット
最後に高卒から公認会計士を目指すことのメリットとデメリットをまとめて紹介します。メリットと同時にデメリットも存在するため、目指すかどうかを決める際はデメリットも併せて確認しましょう。メリットだけをみて決めてしまうと、後々後悔する恐れがあります。収入アップが期待できる
収入アップが期待できることは、大きなメリットと言えるでしょう。公認会計士は取得が困難な難関資格であることから、平均年収は450万円前後だと言われています。高卒者の平均年収は300万円前後のため、公認会計士の資格を取得すれば100万円以上の年収アップが期待できます。将来的に収入を上げたいと考えている人におすすめです。
安定性がある
公認会計士のメリットとしては、安定性が高いことも挙げられます。公認会計士は医師や弁護士、税理士などのように独占業務を持つ職業の1つです。法律で資格を取得していない人では行えない業務が設定されているので、将来的にも需要がなくなるとは考えられません。安定性の高い職に就きたい、確実に食べていける資格を取得したいと考えている人におすすめです。
社会的信用が獲得できる
一般的に高卒者は社会的信用が低いと判断されることがありますが、公認会計士の資格を取得すれば、社会的信用が獲得しやすくなります。社会的信用を上げたいと考えているのであれば、資格の取得を目指してみると良いでしょう。資格取得が困難
公認会計士を目指すことの最大のデメリットは、資格の取得が困難なことです。公認会計士の資格を取得するには、3,000~4,000時間勉強する必要があると言われています。これは単純に計算しても1日2時間の勉強であれば4~5年、1日3時間の勉強であれば3年前後の時間がかかるということです。資格取得に向けて勉強を続けることは決して簡単なことではありません。特に高卒者の場合は、大学を卒業している人と比較して勉強しなければいけない範囲が増える傾向があり、途中で挫折する可能性も少なくありません。