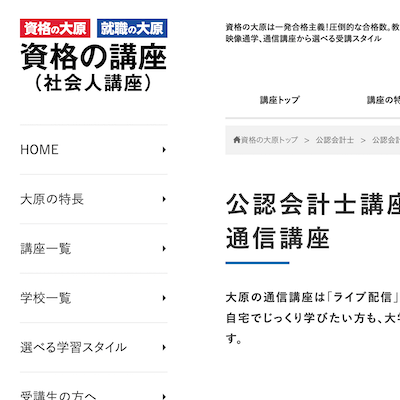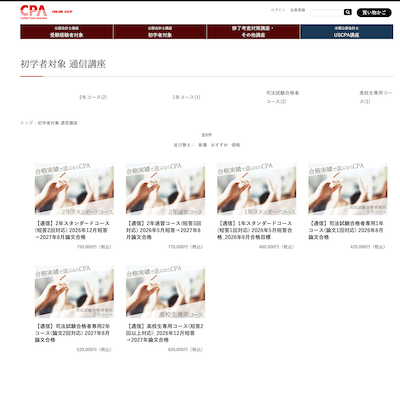公認会計士はキャリアアップや年収向上を目指すうえで魅力的な資格です。しかし、仕事と両立しながらの受験には時間や体力、環境面での課題があります。この記事では、社会人が働きながら公認会計士試験に合格するまでの目安期間や難しさ、成功のポイントについて詳しく解説します。
公認会計士は働きながら取得可能?
公認会計士は社会的に高い信頼をもつ国家資格であり、とくに経理・財務やコンサルティング業界への転職を目指す社会人にとって大きな武器となります。ここでは、その取得の難易度や学習時間の目安について解説します。学習時間は3,000時間以上
公認会計士合格のためには、長時間にわたる学習が求められます。試験合格までに必要な勉強時間は3,000時間以上とされており、平均で2年から4年程度かかるのが一般的です。試験では、まず短答式試験を突破し、その後論文式試験に進む構成であり、それぞれ出題範囲が広く、合格するためには戦略的な学習が欠かせません。よって、社会人が働きながら合格を目指すことは不可能ではないものの、相当な覚悟が必要です。
合格率は10%ほど
公認会計士全体の合格率は10~11%と低く、狭き門です。また、合格者の年齢層を見ると、20代の占める割合が非常に高く、在学中に集中して学習するケースが多いとされています。公認会計士・監査審査会の令和2年度のデータによると、25歳未満での合格が全体の約6割を占めており、30代以降の合格者は減少傾向です。
公認会計士試験合格が働きながらだと難しい理由
働きながら公認会計士試験に合格するのが難しいのは、限られた時間の中で高い学習量をこなし、精神的・肉体的な負担を乗り越えなければならないうえ、試験特有の厳しい制約があるためです。ここでは、その具体的な理由を説明します。勉強時間の多さ
公認会計士試験合格までに必要な総勉強時間は、最低でも3,000時間以上とされています。これは、平日の夜や休日をすべて勉強に充てるほどの覚悟が必要であり、フルタイムで働く社会人が捻出するのは容易ではありません。残業が多かったり、不規則な勤務体系だったりする場合には、計画的な学習がむずかしくなるでしょう。肉体的・精神的な疲労
会社で働いているだけで、かなりのエネルギーを消耗します。加えて帰宅後に試験勉強をこなすとなると、疲労は蓄積し、集中力も持続しにくくなります。公認会計士試験は、非常に広範囲かつ論理的な理解を要するため、気力のない状態ではなかなか身につかないでしょう。時間制限がある
公認会計士試験には時間制限が設けられているため、社会人受験生にとって不利な試験です。短答式試験合格の有効期間は2年間と定められており、この期間内に論文式試験にも合格しないと、再び短答式試験からやり直さなければなりません。また、論文式試験にも合格の有効期限があり、永続的に有効ではありません。つまり、一度の試験で全科目に合格できなければ、次回試験までに科目合格を維持し続ける必要があり、高いモチベーションと勉強時間を保ち続ける必要があります。
働きながら公認会計士の勉強をする方法
公認会計士の資格は、仕事しながら合格を目指すのは非常に困難です。しかし、社会人であっても合格することは不可能ではありません。ここでは、効率的に学習を進める方法を紹介します。勉強時間の確保
公認会計士試験合格までには、3,000時間以上の学習時間が必要とされています。仕事をしながら捻出するには、スケジュールの見直しが重要です。たとえば、早朝の出勤前や仕事後の夜の時間、休日などを勉強にあてる形が一般的です。さらに、勉強時間の質を高めることも大切で、短時間でも集中して取り組める環境づくりが求められます。
職場環境を整える
現在の職場で十分な勉強時間を確保するのがむずかしい場合、資格取得をサポートしてくれる企業に転職するのもひとつの方法です。実際に、監査法人や会計事務所では、公認会計士試験の受験生を積極的に受け入れているところも多くあります。試験勉強中であることがマイナスの評価にならないばかりか、むしろ理解のある環境で働くことで学習と両立しやすくなるケースも少なくありません。
無理のない学習計画を立てる
過密すぎる学習スケジュールでは、途中で破綻してしまいます。理想的なのは、多少の遅れにも対応できるように余裕をもたせたスケジュール設計です。予備日を設けるほか、スケジュール通りに進まない週があってもリカバリーできるように、長めの勉強期間を想定するとよいでしょう。ただし、公認会計士試験には短答式や論文式の科目合格に有効期限があるため、期限を考慮した計画立案が必要です。