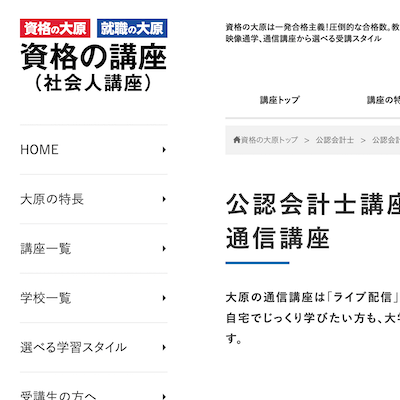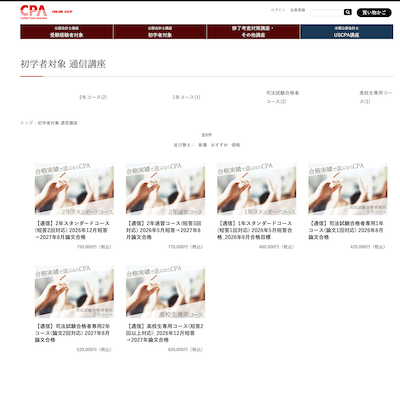公認会計士試験は難易度が非常に高いです。そのため、社会人として働きながら合格を目指す場合は、学習のポイントをしっかりと抑えたうえで効率的に試験対策を進めることが重要です。今回は、働きながら公認会計士を目指す場合の勉強時間や学習のポイント、具体的なスケジュールについても詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
必要な勉強時間はどのくらい?
公認会計士は数ある国家資格の中でも非常に難易度が高く、合格するには十分な勉強時間を確保することが必要です。ここでは、公認会計士合格のために必要な勉強時間や効率的な学習方法について詳しく解説します。公認会計士合格に必要な勉強時間
公認会計士に合格するには、3,000〜5,000時間程度の学習が必要です。1日6時間勉強すると考えても約2年間におよぶ試験勉強が必要となりますが、社会人として働きながらの合格を目指す場合、とくに平日は1日にまとまった勉強時間を確保するのが難しいケースもあるでしょう。たとえば、平日には仕事終わりの2〜3時間、休日には8〜10時間ほど勉強すると考えた場合には、2年または3年ほどかけて合格を目指すのが一般的です。
試験勉強の方法
社会人が公認会計士を目指す場合の勉強方法は、予備校や通信講座を利用する方法または独学の大きく2種類です。予備校はライブ授業やオンライン授業などを通してしっかりと知識を身につけられるほか、過去問分析や生徒の合格実績から積み上げられたノウハウの提供によって効率的な学習が叶います。また、ほかの受講生と接することでモチベーションアップにつながるのもうれしいポイントです。通信講座は予備校に通うのが難しい社会人でも選択しやすい学習方法であり、予備校よりもコストを抑えられます。
ただし、用意されたカリキュラムに沿って効率的に学習を進められるのは予備校と同じですが、自分でスケジュールを管理しなければならないため注意が必要です。独学は高額な費用なしで合格を目指せますが、モチベーション維持やスケジューリング、勉強の効率化などが課題となります。
公認会計士の勉強におけるポイント
公認会計士の試験は複数の科目があるため、それぞれの科目における出題傾向や勉強のポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、公認会計士試験の勉強のポイントについて詳しく解説します。短答式試験のポイント
短答式試験には、財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目があります。財務会計論では簿記の基礎を中心に、実務との結びつきをイメージしながら学習を進めることが重要です。管理会計論は企業の原価計算の流れを重視し、過去問を繰り返し解きましょう。監査論は監査手順を意識しながら過去問を解き、頻出部分をメインとして学習するのがおすすめです。また、企業法では会社法をはじめとする法律関係の問題が出題されるため、これまでの出題傾向を分析しながら知識をしっかりと身につけましょう。
論文式試験のポイント
論文式試験には、会計学・監査論・企業法・租税法の4科目があります。会計学では過去問に繰り返し取り組みながら応用力をつけることが重要です。監査論は論理的な校正と具体的な説明が求められ、企業法では実例に基づいた論文練習と応用力を鍛えることが必要です。また、租税法は法人税の計算やその背景の説明スキルが必要となるため、基礎をしっかりと理解したうえで正確に解答する力が求められます。