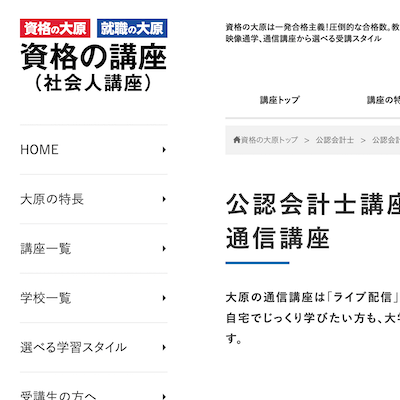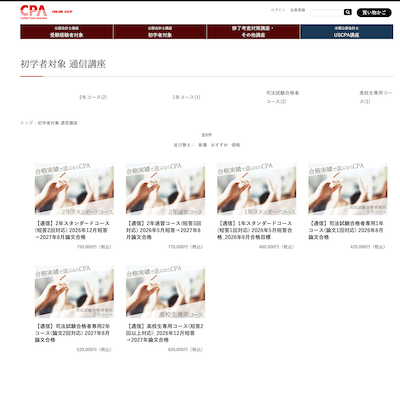公認会計士は、会計・監査のプロとして企業を支える重要な存在です。税務やコンサルなど活躍の場は幅広く、高度な専門知識が求められます。しかし、どんな試験があるのか、どの科目を勉強すればよいのかなど、不安を感じることも少なくありません。この記事では、公認会計士試験の内容を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
公認会計士試験の必須科目
公認会計士になるためには、さまざまな知識とスキルが求められます。試験では、会計の専門知識はもちろんのこと幅広い分野の理解が必要です。しかし、どの科目をどのように学ぶべきなのか悩む人も多いのではないでしょうか。ここでは、公認会計試験で必須とされている5つの科目について詳しく解説します。財務会計論
財務会計論は、帳簿のつけ方や決算書の作成など、会計の基本を学ぶ科目です。大きく分けて簿記と財務諸表論の2つに分かれています。簿記では数字の計算や仕訳のルールを覚え、財務諸表論ではその背景にある理論や考え方を学びます。この2つは内容が深くつながっているため、並行して学習することで理解が進みやすくなります。片方が理解できないと、もう片方を理解するのが困難です。会計士試験の核となる科目なので、最初に重点的に取り組むのが効果的です。
管理会計論
管理会計論では、企業内部の管理に役立つ会計情報の扱い方を学びます。経営の意思決定に直結する内容が中心です。試験では原価計算や予算管理の手法が問われ、製造業をイメージしながら具体的に数字を扱う問題が出題されます。計算力だけでなく、経営の視点も求められるのが特徴です。この科目も財務会計論と同様に2つの試験形式で問われるため、計画的な学習が欠かせません。
監査論
監査論は、公認会計士の実務に直結する知識を扱う科目です。企業が作成した財務書類にミスや不正がないかをチェックする、監査のルールや考え方を学びます。暗記が中心になりますが、単なる知識だけではなく、なぜそうなるのかという背景まで理解することが重要です。範囲が広いため、定期的な復習と基礎の積み重ねがポイントになります。公認会計士が備えるべき価値観を含め、財務諸表監査に関するさまざまなルールの内容や背景を理解しておかなくてはいけません。
企業法
企業法は、会社の運営に関わる法律を扱います。主に会社法や商法、金融商品取引法といった法律が出題範囲です。その中でもとくに重要なのが株式会社に関する規定です。株式会社の設立から運営、消滅にいたるまでの諸規定を学びます。法律の言葉は難しく感じられるかもしれませんが、ルールを正しく理解すれば確実に得点につながる科目でもあります。法律の流れや構成を理解しながら、繰り返し学んでいくことが重要です。
租税法
租税法は、税金に関する知識を問う科目です。法人税、所得税、消費税の3つが中心に含まれており、計算問題が多く出題されます。税法の仕組みや条文の内容も出題されるため、しっかり理解しておかなくてはいけません。試験では実務に近い問題が出されるため、知識を覚えるだけでは得点がとれません。内容が複雑なため、早い段階からの学習が必要です。
公認会計士試験の選択科目
公認会計士試験では、必須科目に加えて選択科目もあります。選択科目は4種類あり、受験者はその中から1つを選んで学習および受験します。どの科目を選ぶかによって勉強量や得意分野が大きく左右されるため、選択は慎重に行う必要があります。それぞれの科目には特徴があるため、事前に内容を知っておくことで、自分に合った戦略を立てることが可能です。
経営学
経営学は、選択科目の中でも最も人気のある科目です。理由は、他の科目と比べて学習範囲が比較的少なめであること、そして財務会計論や管理会計論との相性が良いため並行して勉強しやすいからです。試験では分散や期待値などの基本的な計算問題のほか、企業経営に関する基礎知識が出題されます。数学といっても基礎レベルの内容が中心なので、苦手意識がある人でも取り組みやすいとされています。ただし、試験委員の交代により出題傾向が変わる可能性があるため、過去問を分析する力も求められます。
経済学
経済学では、ミクロ経済とマクロ経済という2つの視点から、経済の仕組みや動きを学びます。ミクロでは個人や企業の行動を分析し、マクロでは国家全体の経済状況を理解します。グラフや数式を用いた問題が多いため、初めは難しく感じることもありますが、基礎をしっかり理解すれば応用も利きやすいでしょう。学習量はやや多めですが、高得点を狙いやすい科目といわれています。とくに数学が得意な人には有利です。一方で、財務会計など他の科目との関連性は低いため、独立して学ぶ姿勢が求められます。1つの間違いで、複数の問題を間違えてしまうリスクがあるため注意が必要です。
民法
民法は、法律分野に興味がある人や、数学が苦手な人に適しています。出題範囲は、民法総則、物権、債権などが中心で、論理的な読解力や法律の考え方を学びます。ただし、民法は覚えるべき条文や判例も多く範囲が広いため、学習に多くの時間を費やすことが必要です。また、選択者の中での競争率も高いため、じっくり時間をかけて学習に取り組まなくてはいけません。
統計学
統計学は、記述統計や確率、推定、回帰分析など、データに基づく分析手法を学ぶ科目です。数字に強い人にとっては得点をかせぎやすく、比較的短期間の学習で試験対策が可能とされています。ただし、確率や数式の理解が求められるため、数学に苦手意識がある人には難しく感じられるかもしれません。内容は実務でも活用されるものが多く、将来のキャリアに役立つ知識を得られる点も魅力のひとつです。試験傾向が比較的安定しており、計画的に学べば得点が伸ばしやすい科目です。また他の試験科目との関連性はあまり見られないため、単独での学習が中心になります。
試験時の出題科目順序
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の2段階に分かれており、それぞれに出題される科目の順番が決まっています。科目の特徴や順序を理解したうえで対策を立てることで、効率よく学習を進められます。事前に出題順を知っておくことで、本番での時間配分にも役立つでしょう。短答式試験の出題科目順序
公認会計士試験の短答式試験では、出題される科目の順番が決まっています。最初に財務会計論が出題され、続いて管理会計論、監査論、企業法の順で進んでいきます。どの科目も基本的な知識と理解が求められるため、出題順をふまえて学習の流れを意識することが大切です。論文式試験の出題科目順序
論文式試験では、まず会計学が出題され、次に監査論、企業法、租税法と続きます。最後に、あらかじめ選択した科目の経営学・経済学・民法・統計学のいずれかを解答します。論文式では計算だけでなく、論理的な説明や文章力も問われるため、それぞれの順序に合わせた準備が必要です。公認会計士で免除される科目
公認会計士試験では、大学や大学院で特定の課程を修了している場合や、司法試験に合格している場合などに、試験科目の一部が免除される制度があります。たとえば、会計系の大学院で所定の単位を取得して修了すると、論文式試験の選択科目が免除されることがあります。また、司法試験合格者には、企業法などの一部科目が免除されるケースもあります。条件や申請手続きについては事前に確認が必要です。
選択科目の選び方を紹介
公認会計士試験では、論文式試験で4つの選択科目の中から1つを選んで受験する必要があります。科目選びは得点に大きく関わるため、慎重に判断することが重要です。自分に合った科目を選ぶことで、効率的に学習でき合格に近づけるでしょう。ここからは、選択科目を選ぶ際の判断基準を3つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。
多くの受験生が選んでいる科目を選ぶ
まず挙げられる判断基準は、受験者数が多い科目を選ぶことです。多くの人が受験する科目は、出題傾向が安定しており、平均点の変動も少ないという特徴があります。とくに経営学は受験者の大多数が選ぶ人気の科目であり、出題内容や難易度に大きなブレが生じにくいため、学習の見通しが立てやすいです。
また。受験者が多い科目はそれだけ教材や過去問、講座の数も豊富です。参考にできる情報が多く、学習を進めやすい環境が整っているのも大きなメリットです。
多くの受験者が一定の点数を取れるよう設計されている傾向にあるため、必須科目に時間を費やしたい場合は、多くの受験生が選んでいる経営学を選択するとよいでしょう。
学習に必要な時間で選ぶ
選択科目を選ぶうえで、勉強にかかる時間を基準にするのも有効な手段です。試験全体の科目数が多いため、できるだけ効率よく学習したいと考える人が多いでしょう。とくに統計学や経済学は、暗記よりも理解・計算が中心になるため、数学が得意な人にとっては比較的短い時間で得点につなげることが可能です。
数学的な考え方に慣れていない場合は学習に時間がかかることもありますが、基礎的な計算力があれば安定した点数を取ることが可能な科目です。暗記科目に比べて応用が利くという点でも、短期間で結果を出したい人に向いています。
自分の得意分野で選ぶ
自分の得意不得意を明確にし、それに合った科目を選ぶことも判断基準のひとつです。選択科目には、それぞれ性質や出題形式に違いがあるため、自分の強みを活かせるものを選ぶと学習の効率も向上します。数学が苦手で暗記が得意な人には民法がおすすめです。民法は法律の理解と記憶が中心となるため、計算問題に悩まされることなく、暗記力を武器に得点を狙うことが可能です。
それに対し、数字に強く論理的思考が得意な人には、統計学が適しています。統計学の問題の大半は計算中心であり、知識の正確さと計算力の両方が試されます。